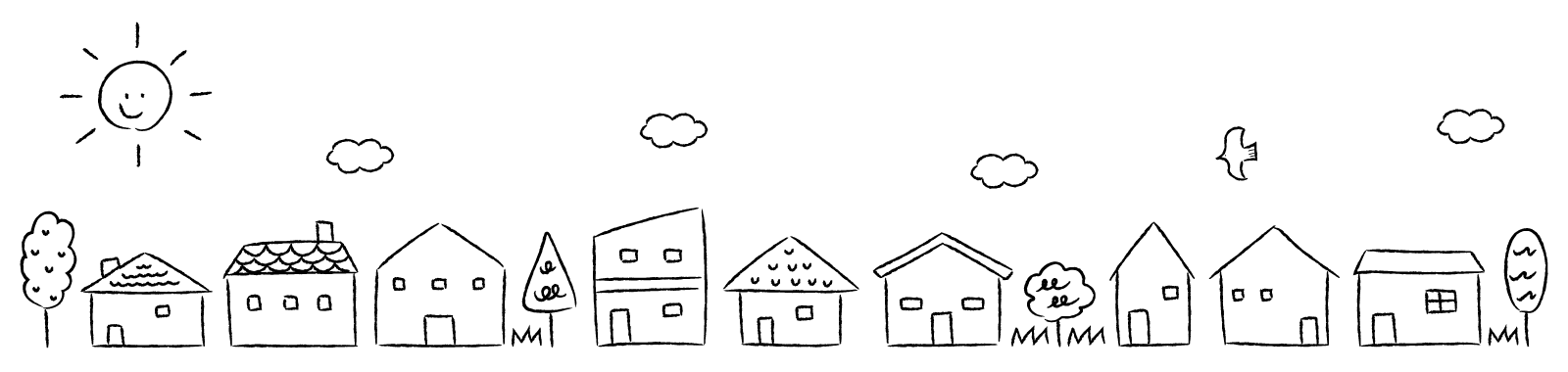おれんじキッズでは、正社員・パートさんを募集しています。
おれんじキッズの始まり
できる事、嫌な事、苦手な事、子どもは一人ひとり違います。なのでこの子にとって何が一番いいのか、何が一番必要かと考えると、ある一つの支援方法が全ての子どもたちに有効だという、そんな魔法の特効薬はないはずです。それさえやっていれば全ての事が成長できるとは思えません。「発達障害」という言葉ですべてをくくり、「ならこれをやればいい」という考え方はやめよう、そんな思いから生まれたのが、今のおれんじキッズです。
結果、TEACCH、ABA、PECS、感覚統合、行動療法、作業療法、言語療法などなど、今では様々な理論やプログラムを使って支援を行っています。というと何だか偉そうですが、この子にはこれが必要ではないか、この子には…とやっているうちに色んなプログラムがだんだん増えたというのが実際のところです。ただ大事なことは、「プログラムがある」ということではなく、その理論やスキルを習得したスタッフが、目の前の子どもに対してきちんと確実に“実践できているか”です。「知識はあるけど子どもの扱いは苦手」「子どもは好きだけど理論は知らない」などよく聞く話です。理論を確実に理解し、こどもに対して実践できる、その知識とスキルの習得には、日々職場で先輩から教わったり、たまに開かれる研修会に参加したり、市販の本を読んだだけで習得できるような、そんな簡単なものではありません。一つの理論を一から学び、全体を理解し、更に実践できるまでには膨大な時間を要します。それは私たちにはとても難しいことでした。
子ども一人ひとりに合わせた支援のために
子ども一人ひとり異なるプログラムを計画、実践、記録、検証し、また計画を行う。保護者の相談、関係機関との連携、季節の楽しいイベント、集団活動、余暇活動、様々な制作物、食事介助、トイレ介助、毎日の送迎表の作成と実際の送迎業務、社内会議や研修、事業所全体の準備、清掃、事業所や会社の書類仕事、関係業務などなど。更におれんじキッズは多機能事業所なので営業時間の最初から最後まで子ども達の支援を行っています。そうした合間をぬって勉強時間を確保することが本当に難しい事でした。
そこで、本来の基準人員を大幅に超えるスタッフを置き、支援の質と量を確保しながらその分を勉強に充て、また東京、名古屋、大阪、福岡など全国に研修に行き、逆に東京からも海外からも講師を招いて学びました。もちろんその人件費、資格取得の費用、教材費、旅費など全て会社で負担します。それは膨大なコストです。全ては一人ひとりに合わせた支援のために。当然ですが、スタッフみんなが、それだけ勉強するために努力したということは言うまでもありません。みんな必死でした。
事業所運営の考え方
私たちが行う事業は、1日の利用人数も利用料金も、国が定めたルールで決まっています。 売れば売るほど収入が上がるというような商売ではありません。サラリーマンのご家庭と同じ、 毎月決まった財布の中で色々やりくりをしながら経営することが必要です。僕自身も資産家ではなく、サラリーマン家庭で育った、宝くじが当たることを願うただの一般人です。使えるお金は限られています。一方、保護者の皆さんのニーズは多岐にわたります。「子どもに自立してほしい」「成長してほしい」というお子様に関するニーズもあれば、「長時間預かってほしい」「休みの日も預かってほしい」「送迎してほしい」というご家庭の事情など本当に様々です。ですが、先述のとおり、何かを行えば何かを我慢しなければなりません。長時間の営業や土日の営業はできていませんし、送迎も完璧ではありません。そうした運営に対して「長時間預かり送迎をするのが放デイとして当たり前だ」とご批判をいただいたこともあります。ただおれんじキッズでは、そうした考え方はしていません。もちろんそんな国のルールもありません。もちろん、出来る事ならすべてのニーズにお応えしたいと思いますが、実現ができていません。
誤解があってはいけないのですが、何かの考えが正しくて、何かの考えが間違っているという事ではありません。一人ひとり色んな事情や環境があるので、様々な考え方や色々な事業所があって当然だし、全て正しいと思います。ただただ、全ては出来ないので何かを優先せざるを得ないということです。色んなものに手を出して全てが中途半端になったり、なんでもやりますと言いながら結局何にもできない、そんなことになってはいけないという思いです。
こうした私たちの考え方にご理解をいただき通ってくださるご利用者の皆様には感謝しかありません。その分、学びを進めることに責任が生じますが、精一杯取り組んでいるスタッフの皆さんにも本当に有難いと思っています。
おれんじキッズの支援が目指すもの
私たちが目の前のお子様と過ごす時間は限られていますが、親御さんは30年、40年と長い時間をお子様と一緒に暮らしていくことになります。その長い時間がお互いに少しでも楽しいものになるように、思い出が沢山つくれるように、お子様の成長のため、生きていく力を身に付けるために今私たちが出来る精一杯のサポートをしよう。そしてお母さんの「なぜなんだろう」「どうしたらいいんだろう」という悩みを少しでも解決しようという考えです。人から認められること、大好きな人と少しでも長く一緒に時間が過ごせることはかけがいのないものです。弊社のスタッフには障害のあるお子様の母が何人かいますが、想いはみんな同じです。
例えば子どもに対する理解一つとっても、「私はこう思う」「私はこうだ」と話し合うことはいいことですが、極力個人の感想や主観を取り除き、客観的かつ科学的根拠をもって判断されないと、見方はスタッフみんな違うので、“見る人が違ったらその都度違う”みたいなことが起こります。“見る人が変わるとその子が変わる”のはおかしいですよね。誰が見ようが、その子はその子なのだから。
だからこそ私たちは、学びと経験を積み重ねなければなりません。ただ知識やスキルにゴールはないので終わりがありません。でもみんなで流した汗が、子ども達の成長のサポートに、また保護者の方からの相談のお役に立つことに、全て帰結すると考えています。
理事長から皆様へ
長文におつきあいいただき、ありがとうございました。これが私たちおれんじキッズの歴史と現状です。偉そうなことを長々書きましたが、私たちはまだまだ未熟で、道半ばです。私たちも子ども達と一緒に、一日一日成長していきたいと思っています。そんなおれんじキッズで、子ども達の成長のため、保護者の方の悩みの解決のために働きたい、学びたいと思われる方がおられましたら、ぜひおれんじキッズの門をたたいてください。お待ちしております。
一般社団法人ともに進む舎
理事長